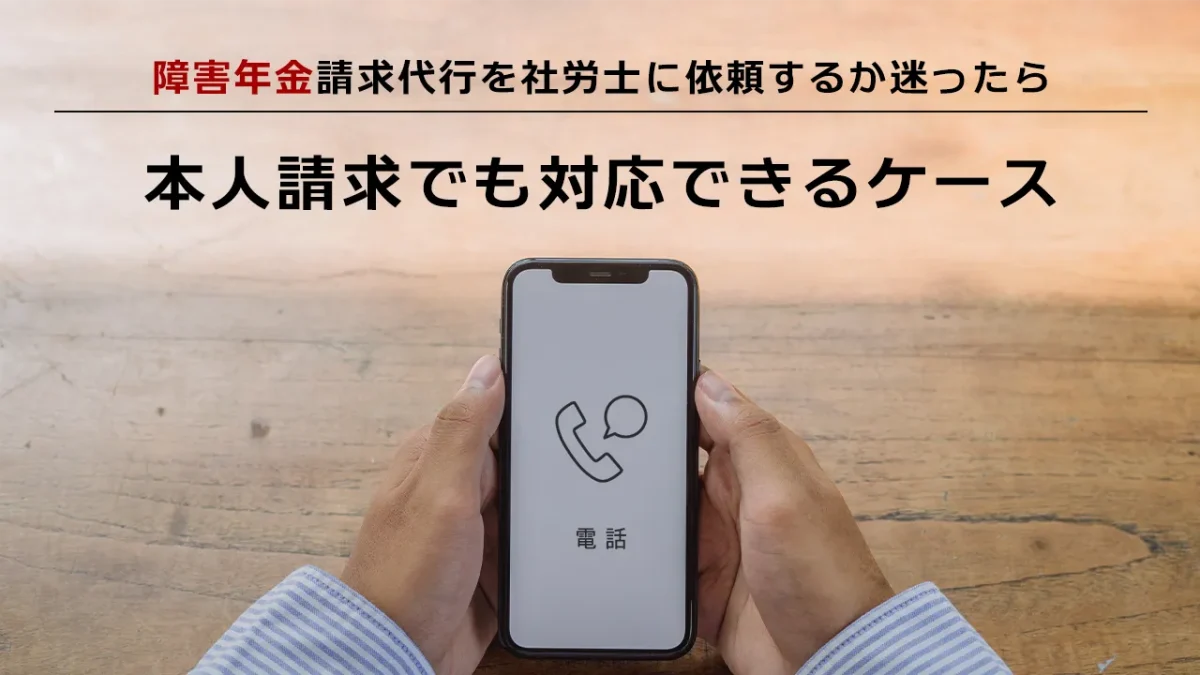社労士への依頼が必要ないケースもある
去年から続く障害年金審査の変化について、一般の方が一つひとつ把握し対策・対応することは難しく、障害年金専門の社労士への期待値は以前にも増していっそう高まっていると感じています。
しかし、障害年金に関してすべてのケースで社労士の活用をお勧めするわけではありません。
今回は、社労士に依頼しなくても対応できるケースをまとめました。障害年金手続きに関して社労士への依頼を迷ったら参考にしてみてください。
1本来請求(障害認定日から1年以内の手続き)
障害年金は障害認定日(初診日から1年6か月後または20歳到達日のどちらか遅い方)以降に請求することができます。障害認定日から1年以内に請求する方法を本来請求といい、診断書は1枚のみで審査され、認定されると障害認定日の翌月に遡って支給されます。
時間的余裕がある請求方法なので、本人やご家族等のペースで取り組むことができます。
社労士活用のメリットとして、本人やご家族等に比べて、手続き開始から完了まで1~2か月間の時間短縮効果が期待でき、事後重症請求の場合は短縮した1~2か月分の年金を多くもらえる可能性があります。一方、本来請求は時間短縮しても受給月数に変化はなく、社労士活用ついて金銭的なメリットはありません。
2再認定(更新)
再認定(更新)の支給停止割合はわずか1.1%で「審査」というより「確認」の意味合いが強いです。前回と比べて、就労状況に変化がなく、診断書内容が大幅に軽くなる等を除き同じ等級で更新できる可能性が高いです。
ただし、前回と異なる医療機関に障害状態確認届(更新用診断書)の作成を依頼する場合、必ず前回の診断書コピーを一緒に渡すようにしましょう。完成した障害状態確認届を受け取ったら、念のため前回の診断書コピーと比較し、大きな変化がないか確認することをお勧めします。
3ご家族など周囲の手厚い援助が得られる
障害年金の手続きには何度も年金事務所、医療機関などに足を運ぶなど身体的な負担と、病歴・就労状況等申立書作成時に辛い記憶を文字にする精神的負担がネックになります。特に後者は体調を悪化させてしまうことがあるので注意が必要です。
このことが原因で手続きが頓挫してしまい、何年も手つかずのままになっている方がいらっしゃるのは残念です。
周囲に親身になってくれる家族や医療機関のソーシャルワーカー等支援者がいれば、サポートをお願いしてみてください。
もし、サポートしてくれる家族や支援者がいない場合は社労士の活用をご検討ください。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士